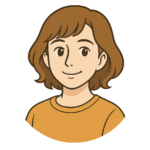介護職が続かないのはなぜ?10年の現場経験から見た本当の理由と対処法

はじめに
介護の仕事は「やりがいがある」と言われる一方で、長く続けるのが難しい職種でもあります。私自身、介護の現場に10年ほど関わり、多くの人の入職と退職を見てきました。仕事が嫌いで辞める人ばかりではなく、真面目で優しい人ほど続けられなくなってしまうことも少なくありません。
この記事では、そんな経験から見えてきた「介護職が続かない理由」と「続けるための考え方」について、より深く掘り下げてお伝えします。
この記事でわかること
- 介護職が続かない主な原因と、その背景にある現場の構造
- 続けられる人に共通する考え方と行動の特徴
- 明日から実践できる、心と体を守るための具体的な工夫
介護職は本当に続かないのか?現場の実情

厚生労働省の統計によると、介護職の離職率はおおよそ15〜16%前後で推移しています。これは全産業平均よりやや高く、職場によっては3年以内に半数が入れ替わるところもあります。現場にいると、数字以上に「人が定着しない」という実感があります。
私が経験した中には、ある施設で中途採用した新人が1週間で辞めてしまう、教育係も定着せず入れ替わっていたこともありました。感覚的ですが1~2か月に1人は退職していました。原因は待遇だけでなく、現場の空気感や人間関係など、目に見えにくい部分が多いのです。介護は「人を支える仕事」ですが、その人を支える側のケアが足りていない職場も少なくありません。
ただし、すべての職場が悪いわけではありません。良い環境では10年以上勤める職員も多く、職場の雰囲気や体制で大きく差が出ます。続かないのは“人の弱さ”ではなく、“環境と支援のバランス”が崩れていることが多いのです。
続かない理由① 体力的な限界を感じる
介護の現場は、想像以上に体力を使います。夜勤で睡眠リズムが乱れたり、入浴介助や移乗で腰を痛めたり。若いころは何とかできても、年齢とともに体の疲れが抜けなくなります。
私が働いていた施設でも、腰や肩を痛めて体調不要になる人、ぎっくり腰が原因で退職する人が少なからずいました。体力的に厳しい仕事だからこそ、「無理をしない」「助けを求める」姿勢が大切です。自分が倒れてしまっては利用者さんを支えることもできません。介護は“チームプレー”です。1人で抱えずに「ちょっと手を貸して」と言える雰囲気がある職場を選ぶことが、長く続ける第一歩です。
さらに、体力の問題は単に「疲れる」というレベルにとどまりません。慢性的な腰痛や膝痛を抱えたまま働くと、私生活にも支障が出ます。これが「もう無理だ」と感じる大きな引き金になるのです。リフトやスライディングシートなどの福祉機器を導入している施設かどうかも、続けやすさに直結します。
続かない理由② 人間関係で消耗する
介護職の離職理由で最も多いのが、人間関係のトラブルです。施設長より発言力のあるベテラン職員の圧力、派閥、言葉のきつい上司──こうした職場は少なくありません。現場ではチームワークが欠かせない分、人との距離感が難しいのです。
私の経験でも、「介護の仕事自体は好きだけれど、職場の雰囲気がつらくて辞めた」という人を多く見てきました。ある同僚は、利用者さんから信頼される優しい人でしたが、職場内の人間関係に嫌気がして退職してしまいました。人間関係のストレスは、体の疲れよりも心を削ります。
人間関係を良くするために大切なのは、「相手を変えようとしない」ことです。職場にはいろいろな価値観の人がいて当然です。意見が合わない人とは距離を置き、信頼できる人と協力しながら仕事を進めるほうが、結果的に自分を守ることにつながります。もしどうしても合わない場合は、「転職」も立派な選択肢です。環境が変わるだけで、仕事がまた好きになれることもあります。
続かない理由③ 給料と責任のバランスが取れない
介護の仕事は責任が重いのに、給料が低い──これは業界全体の課題です。夜勤手当や処遇改善加算で以前よりは良くなってきましたが、それでも「仕事量と収入が見合わない」と感じる人は多いです。
ある若手職員は、夜勤を月に6回こなしても手取りが20万円前後でした。利用者さんの体調が急変することもあり、夜勤のプレッシャーはかなりのものです。命を預かる責任を考えると、決して十分とは言えません。しかも、介護の現場では「感謝の言葉」が励みになる反面、ミスをすれば厳しく叱責されることもあります。この精神的プレッシャーが続くと、金銭面だけでなく心の疲労も積み重なります。
それでも、介護職を続けている人の多くは「お金では測れないやりがい」を感じています。大切なのは、自分の生活を守りながら働くこと。資格取得や夜勤回数の調整、副業の検討など、働き方を工夫して“バランスをとる”視点が欠かせません。
続かない理由④ 理想と現実のギャップ
「利用者さんに寄り添いたい」「笑顔で支えたい」──そんな思いで介護の世界に入る人は多いです。しかし、現場に入ると時間や人手が足りず、理想どおりのケアができない現実に直面します。
私自身も、入職当初は「もっと丁寧に関わりたい」と思いながらも、忙しさに追われて流れ作業になってしまうことがありました。夜勤は持ち場が2人体制ですが、すべての利用者に寄り添う余裕がないことも多いです。そんな中で、「自分は何のために介護をしているのか」と迷い、燃え尽きてしまう人も少なくありません。
このギャップを埋めるには、“理想の持ち方”を変えることです。「完璧に寄り添う」ではなく、「できる範囲でベストを尽くす」と考える。たとえば、1日1回でも笑顔を交わせたら十分。それが積み重なることで、利用者さんの信頼や自分の自信につながっていきます。
続かない理由⑤ 教育・サポート体制の不足
新人教育が整っていない施設では、入ってすぐに放置されることもあります。教える側にも余裕がなく、「見て覚えて」と言われて戸惑う人も多いでしょう。これでは不安や孤独感が募るばかりです。
ある新人さんは、初日からいきなり食事介助を任され、注意されるたびに自信を失っていきました。「どうすればいいか分からないのに怒られる」──そんな経験を重ねると、誰でも辞めたくなります。介護の現場では、人を育てる時間を確保することが難しいため、どうしても新人が孤立しがちです。
こうした環境が続くと、やる気のある人ほど疲れてしまい、離職につながります。施設側の課題でもありますが、働く側も「教えてもらえる環境か」を面接時に見極めることが大切です。見学の際に、職員同士の会話の雰囲気や、新人への声かけの様子を観察してみると、良い職場かどうかがわかります。
続けられる人に共通する3つの特徴

以下は、私が現場で感じた「続かない人」と「続けられる人」の違いをまとめた比較表です。読んでみると、自分の傾向やこれからの工夫点が見えてくるかもしれません。
| 項目 | 続かない人の特徴 | 続けられる人の特徴 |
|---|---|---|
| 考え方 | 理想を高く持ちすぎて自分を追い詰める | 「できる範囲でベストを尽くす」と柔軟に考える |
| 人間関係 | すべての人と合わなければと無理をする | 信頼できる人を見つけて距離を保つ |
| 働き方 | 助けを求めず一人で抱え込む | 周囲に相談し、チームで分担する |
| ストレス対処 | 我慢し続けて限界まで耐える | 休息・趣味・会話でリセットする |
| 成長意識 | 失敗を恐れて行動できない | 小さな成功を積み重ねて自信をつける |
10年の経験の中で、「この人は長く続くだろうな」と感じた人には共通点がありました。彼らは決して特別なスキルを持っているわけではなく、日々の中で小さな工夫を積み重ねているのです。
① 相談できる人を持っている
一人で抱え込まず、上司・同僚・家族など、誰かに相談できる人ほど長続きします。介護はチームで行う仕事です。悩みを共有できる相手がいるだけで、気持ちはずっと軽くなります。私の知る長年勤務のベテランさんは、困ったことがあると必ず誰かに相談し、「愚痴ではなく共有」として話していました。これが結果的に人間関係を良くするコツにもなっています。
② 完璧を目指さず、割り切れる
「利用者さんのために全部やらなきゃ」と思う人ほど疲れてしまいます。できること・できないことを区別し、「今日はここまで頑張れた」と自分を認められる人は、燃え尽きにくいです。完璧を求めると、少しのミスで自分を責めてしまう。逆に、「できたこと」に目を向ける人は前向きな気持ちを保てます。
③ 小さな喜びを見つけられる
利用者さんの「ありがとう」「笑顔」「手を握ってくれた瞬間」──そうした小さな出来事に喜びを感じられる人は強いです。報われない日があっても、誰かの一言でまた頑張れる。私も何度もその言葉に救われました。仕事の中で見つけた小さな幸せを、自分の中で大切にしていくことが、長く続ける力になります。
おわりに:辞めてもいい、続けてもいい

介護の仕事は、人の人生に深く関わる尊い仕事です。でも、それと同じくらい、心身に負担がかかる現場でもあります。辞める選択をすることも、決して悪いことではありません。大切なのは、「なぜ続けたいのか」「何がつらいのか」を自分の中で整理することです。
10年の現場を通して私が感じたのは、「無理をして続けるより、自分を大切にする勇気」のほうがずっと大事だということ。辞めた経験があっても、それは決して失敗ではありません。その経験は、次に進むための糧になります。介護職を続けるにしても離れるにしても、その経験は必ず誰かの支えになります。どうか自分を責めずに、今の一歩を大切にしてください。
介護の仕事を続けるということは、「利用者の尊厳を支える」と同時に、「自分の尊厳を守る」ことでもあります。あなたの選択が、どうか優しさと希望につながりますように。